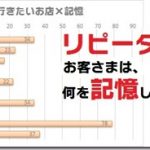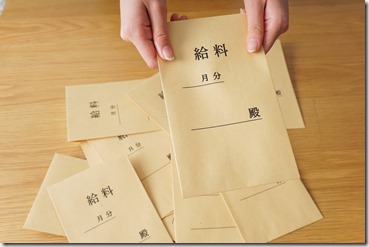飲食店において、人は宝です。
さて、教育において、何が一番大切かというと、
「準備」に他なりません。
その「準備」を怠っているお店によくある新人の迎え入れる状況はこんな感じです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新人:こんにちは〇〇です。
店長:あ、〇〇くんね、ちょっと待ってね。今ちょうど忙しくて。
新人:はい。
店長:Aさん、ちょっといい?今新人さんが来たから、今私がしているこれ変わってくれる?
(パートの)Aさん:はい、でもわたし4時で上がりです。
店長:ごめん、5時まで延ばせない?
Aさん:えーー・・・急に言われても。
店長:ごめん時給1時間別につけるからお願い!
Aさん:もーー。わかりました。
店長:〇〇さん、今日がはじめてだよね、「お店のルールブック」は渡しておいたかね?
新人:まだです。
店長:そうだったかね、ちょっと待って印刷するから。それから靴のサイズは何センチ?
新人:26です。
店長:じゃ、発注するけど、今日のところは、Bくんの分を借りといて。
新人:はい。
店長:制服を合わせようかね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
という感じです。
すべて後手後手ですね。
採用が決まったら、事前にすることは少なくともですが
1.労働契約書を締結する。
2.最小限のお店のルールを説明する。(もしくはルールブックを渡しておく。)
※髪の毛、アクセサリーなど許可範囲を説明する。
3.靴・制服を採寸し、発注しておく。
4.私物の収納場所(ロッカーなど)の確保をする。
5.スケジュール調整
※はじめの教育は、必ずマンツーマンでやり、他の業務はしないことが重要。
以上の準備は絶対です。
その上で教育には4つのステップがあります。
「準備」→「説明」→「実行」→「フォロー」です。
その教育の4つのステップを回し続けるのです。
トレーナーはできれば独りが理想ですが、複数設定するにしても、
必ず、責任者は一人選任したほうが良いです。
その責任者は、店長ではいけません。
必ずパートさんかアルバイトさんにします。
そうすることで、教える側であるパートさん、アルバイトさんの不足知識や
何が「正」なのかを再確認させる意味もあります。
よく教育で使われる言葉で、
「本当はこうしなくちゃいけないんだけど、今はみんなこうしてる・・・」
ということがしばしば起こります。
そんなことが、再認識され、マニュアルを修正すべきか、現実を修正すべきか・・・
そのとき初めて、会社がどうするかを決めなくてはいけない。
教育する現場は、全体を修正するいい機会でもあるのです。
ですから、店長は、できる限りパートさんやアルバイトさんに教育をさせなくてはいけないのです。
しかし、教育がうまくいっているか、そのレベルに達しているのかどうかの確認は、
店長が判断すべきです。
そして、レベルに達してない場合、原因を追求する姿勢は抑えて、トレーナーであるパートアルバイトさんと面談して、教育の補習スケジューリングをやり直さなくてはいけません。
そうやっていけば、お店の全体のレベルは上がっていきます。
教育は、あくまでもお店の効率性向上とお客さまへどう心地よく接客できるようにするかが目的であって、
欠員を補充するのが目的であっては、目的を全うしていないと思うのです。