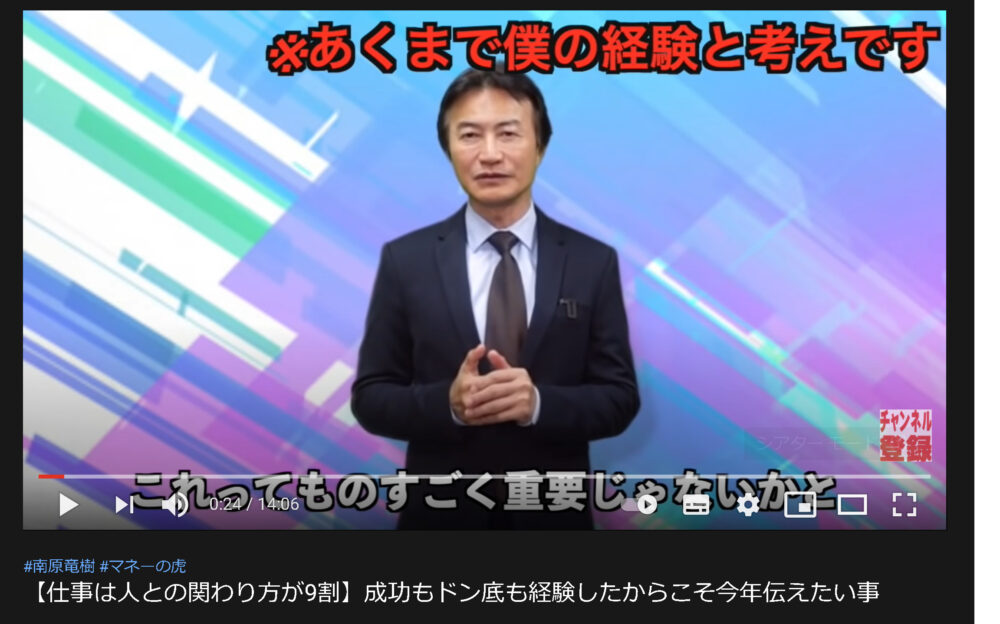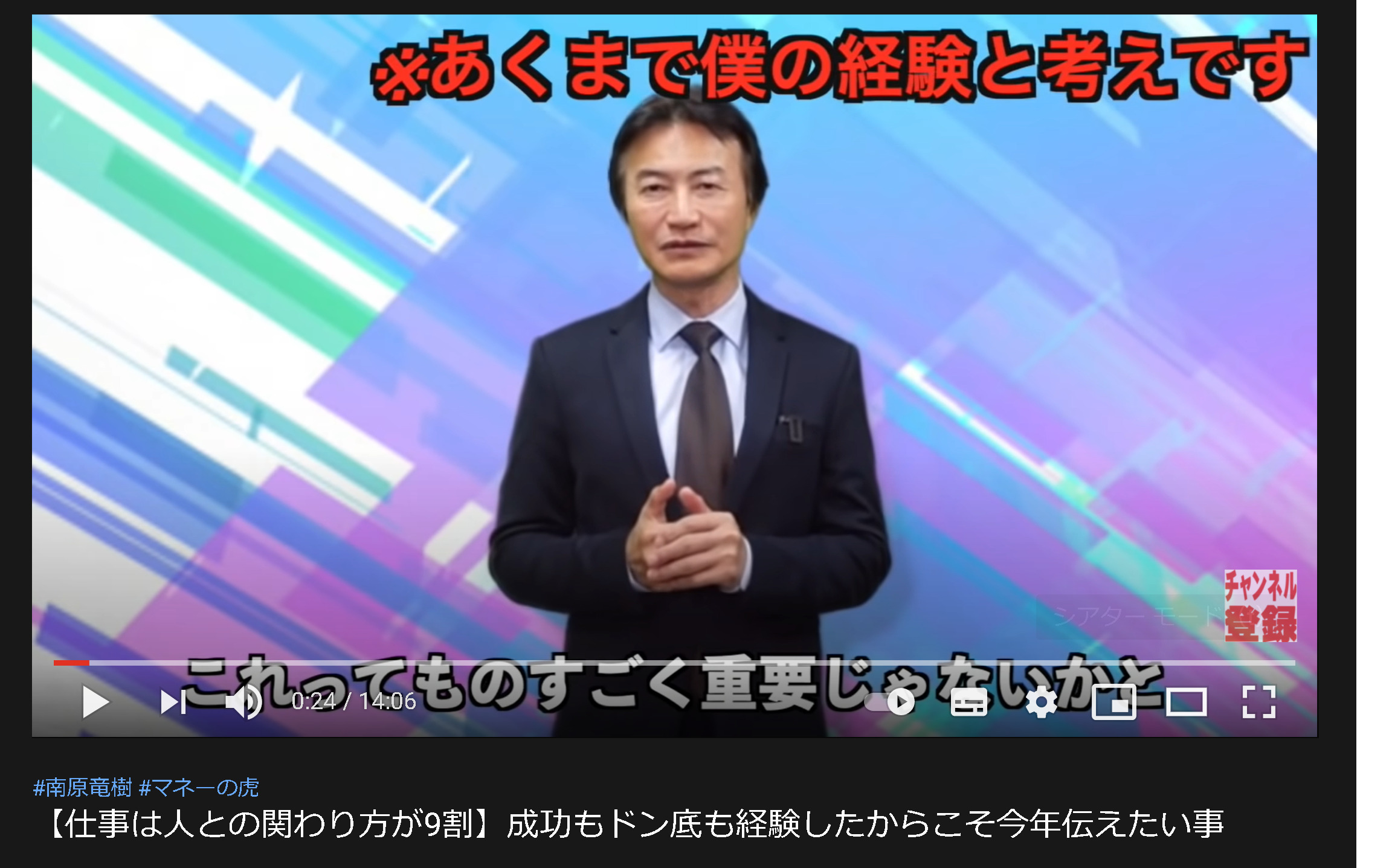南原社長は、かつて「マネーの虎」に出ておられましたよね。
その中でも、表情は優し気で、でも冷徹そうな目が印象的でした。
私のような、小者が味わってない浮き沈みを乗り越えてこられただけあって、
言葉の重みが断然違うなぁと思いましたね。
飲食業の世界も、あまたの小さい店舗からチェーン店まで様々ですが、皆さんそれぞれの成功の形があると思うのですが、やはり、少なくとも数店舗のオーナーになりたいのが夢の人は多いと思います。
そういう志を抱いている方々には、ほんと役に立つお話だと思って、書き留めてみました。
少しでもお役に立てたら幸いです。
僕(南原社長)の事業について
僕はいろいろと事業を成長させてきました。
事業の成長の要、つまりこれは人です。
その「人」の話を今日はしていきたいと思っています。
おはようございます南原竜樹です。
僕はなんとですね、こう見えてもおおよそ40年ぐらい事業をやってきたんです。
そんな中で、人との付き合い方これってものすごく重要じゃないかと。
こんなところをお話しさせて頂きたいと思っています。
事業の立ち上げの時の想い
立ち上げの時、僕が昔ですね自動車屋さんで駆け出しの頃に、僕の少し先輩が、「家にはろくな奴がこんでかんわ」これ名古屋でなんですけども、「うちにはろくな奴が来ないと、彼は採用でいい人が来ない」っていうのをぼやいていたんですね。
僕は彼に言ったんですね、「それ当たり前じゃないか」と「お前のところにろくな奴が来るわけねーだろ」と。
何故かというとですね、彼の会社を見て下さい。
こんなイメージで草っぱらの後ろに、掘っ立て小屋がある中古車屋さんなんですね。

そこに優秀な社員が来てくれるわけもないと、まぁそんな事は当たり前の事なんですけども。
これってステージごとの採用をきちんと戦略として考えてなきゃいけないと。
例えばですね、自分で仕事を始めた時、一人目を採用します。
これって人生においてものすごく大きな階段なんですね。
つまり今まで一人で頑張ってやればよかったと、一人だけの会社、それがなんと人に対して責任を持っていくと。
一人目の人を雇う時、僕が希望する人はどんな人かって言うと、どんな人でもいいんです、ただ24時間365日一緒に働いてくれる人、つまりですね自分のパートナーのように働いてくれる人。
共同経営みたいな形でしたら労働基準法は関係ない。
役員に対してはですね労基法って関係ない、でもそれに対して会社の夢を共有化していくとかアイデンティティを共有していくとかですね、そんなことができる人。
それに対して例えばパソコンがうまいとかですね、戦略が立てられるとかそういったことはあまり関係ないんじゃないかと。
事業が大きくなっていく過程
20人とかそういった規模になった時、会社がどんどんどんどん大きくなっていきます。
順調に会社が伸びたとしましょう。
そうするとですね、最初のうちは自分よりも仕事ができる人は多分一人もいないと思います。
自分がこう頑張って働きます。
自分がすごく優秀で、自分がいろんなことを考えます。
自分の代わりにこんなことを考えてくれる人っていうのはなかなか採用しにくいんですね。
だからそういった仲間とですね、こう頑張っていきながら、自分がとにかく決断を下していく。
決断していかなければ、なかなか事業というのは前方向に進んで行かない。
だからあくまで決定して進んでいく。
つまりですね、みんなを引っ張っていく、それは自分一人だとそこはちゃんと肝に銘じて、そこに対して人に責任をなすりつけたりとかですね、「お前ができないからだ」とかこんなこと絶対に言っては駄目だと思っています。
ただですね、人がどんどん増えてきて、例えば色んな業種によって変わってくると思います。
IT 系とか、おそらくですね想像すると、わりに小さな段階で、そういった自分よりも優秀な人を採用していく。
例えば、自動車さん、5人ぐらいのうちはですね、自分が最も優秀なセールスマンです。
社員には何をしてもらうかって言うと、納車の準備とか車を洗ってもらったりとかですね、簡単な整備とか。
その頃はですね、僕なんかがですね一番の整備士で、一番の営業マンでした。
ところがですね、どんどん会社が大きくなってくるとですね、ある日こんなことが起きるんですね。
僕は歩いていてですね、整備しているお兄さんにですね、「これって本当はここが壊れてんじゃないの、ここを見たらどうだ。」って自信満々に言ったんですね。
すると、彼が言い返しました。
「社長それは違うと思います。たぶん僕はここだと思います。」
それで当時のベンツにですね、こんなでっかいテスターをガチャンと嵌めてですね、テスターの結果を見たら、なんと彼の言う通りだったんですね。
つまり、その時にですね、一つ大きなことが逆転しました。
自動車の整備に関して言えば彼の方が優秀でした。
ただ、まだですね、営業マンとしては、その当時僕が一番優秀でした。
ところがまた月日が経つとですね、ある時なんと、僕よりも車を売るセールスマンが来たんですね。
彼は生き馬の目を抜くようなですね先物業界というところで営業していたんですが、ある時彼が先物を売りに来たんですね。
で、あまりにもの営業力に、「いやいや、そんなね、先物を売っているよりも、うちで車を売ろうよ。お前車も好きだろ。」と言ったら、転身してくれて、うちで車を売るようになりました。
そしたらあっという間に、ナンバーワンセールスマンになったんですね。
つまり、僕よりも車の修理ができるひと、それから僕よりも営業ができる人。
当時ですねまだ事業の計画を考えるのは僕は一番上でした。
ところが、その後にですね、その事業の計画を落としてくひと、つまり銀行さんを説得するためにですね、作る資料、こういった資料を作るのが僕よりもうまい人も出てきた。
そうなってくると、僕を支えてくれるこの3人、僕がですねそう3人と力を合わせてさらに会社を大きくすることができるようになりました。
つまり、そうやって大きくなっていくんですね。
それに会社の力量以上の人を採用することはできないです。
こんなやつしか来ないのか、そうやってぼやいている経営者は全く駄目駄目です。
ひょっとしてあなたの会社の上司や社長が、そんなことを言っていれば、その会社に将来はないと思ってます。
権限委譲ができるようになった時
その後ですねいろんな裁量権を与えるようになってきました。
責任と権限を与えるんですね、そうすることによって企業が成長していくと。
ただこれ口でいうのは簡単なんですが、なかなか経営者としてはですねそういったことに対してドキドキしているんですね。
それがたとえ一つや二つ失敗しても、その失敗を許さないような気持ちで対応してたんでは、全く成長性はなくなります。
つまりそういったことを失敗して、それを学んでいただいて、どんどんどの彼も成長してくれた。
つまり企業の成長と言うのはですね、人の成長をも伴って一緒に成長していかないとなかなか成長できないんです。
組織を強固にする
さらに組織図を作っていきます。
もちろんそれまでにも組織図というものあるんですが、さらに詳細かつ堅牢な組織を作っていかなくてはいけない。
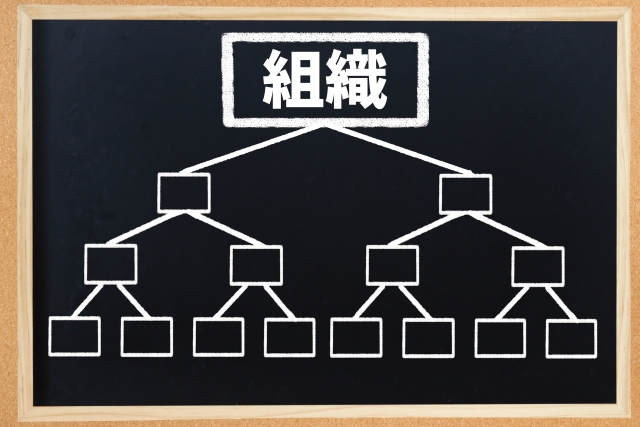
それによってですね、企業というのは成長の限界を超えて行きます。
つまりですね、南原竜樹がその限界のボトルネックになっていたと。
それを超えていいった会社の成長戦略が描かれていく。
そうすると面白くなりますよ、いろんな人たちがですね、いろんな提案を出してどんどんどんどん事業を進めていきます。
そうすることによって、自分の限界を遥かに超えた事業の進捗になってくるんですね。

そうするとですね、僕が沖縄でレンタカー屋さんをやっていました。
非常にシンプルなビジネスなんですが、最終的にはですね沖縄と北海道に拠点を持つですね、結構な規模のレンタカー屋さん、1日の出発台数がなんと1,000台近くなっている。
沖縄ではですね、1位の出発台数になっていたという。
これぐらいのレンタカー屋さんになっていったんですね。
でも、ここは、例えば僕一人だけが会社を引っ張っていたら、とてもできることではないです。
きちんと組織として皆で考えていて、次にああしたいこうしたい、これをやればさらに拡大ができるんだ、とかみんなで協議ができるようになると、会社というのは面白いように成長していきます。
社外の人とのよい関係が好循環をもたらす
そうしていく中で、もちろん会社というのはですね自分達だけでやっていくものではないです。
いろんな取引先が出てきます。
そんな取引先と付き合いたいなーとか、こんな取引先にお願いされたなーとか、こんなことがしたいなー、そういったことがものすごくたくさん出てくるんですよね。
大家さんとの取引、僕はですねチェッカーモータースというイタリアのイメージ的にはこの車ですね、その車を、日本で一番たくさん売ってました。
その頃チェッカーモータースはですね、田園調布日本車を持っていました。
なんとですね、そこからすぐ近くに工場も持っていたんですね。
世田谷区に大きな工場、これ、なかなか持てない。
なら他の外車さんは横浜の随分端っことかまで車を持ってって修理をしたりしていました。
僕はそこの大家さんと非常に良い付き合いをさせて頂いていたんですね。
ところがですね、その田園調布のアルファロメオのディーラーを手放した時、その後なんとそのディーラーが、大家さんから工場の敷地を返してくれって言われたそうなんですね。
つまりそこに付き合いが無くなったからだと思うんです。

その経験もあってですね、僕は沖縄でレンタカー屋さんを始めました。
レンタカー屋さんというのはですね、まあ見ての通りたくさんの敷地が要ります。
最初に何をしたかっていうと、まずは僕、大家さんにご挨拶に行ったんですね。
その土地はいくつかの区画に分かれていまして、何人かの大家さんがいました。
東京からお土産を買ってきて、と言ってもそんなに高いもんじゃないですよ、東京バナナっていう、空港でたくさん売ってますよね、これですこれ、1個1000円ぐらい。

これを5個買ってですね、大家さんに「東京から来ました、ありがとうございました。」って言って配るんですね。
で、また来月も、「東京から来ました、ありがとうございました。」
で、なかなか沖縄というところは排他的な土地で、「内地の人かね」って言ってですね、なかなか土地を貸してくれないんですね。
「内地の人に土地を貸すのはね~」みたいな形で。

ところがですね、そうやっていつもお菓子を配っていて、いつもその沖縄のレンタカー屋の周りでですね、なんかの作物を作ってるおばさんにですね、「おばさんにもあげるよって、お菓子をあげてたんですね。」
そうしたら、そのおばさんが、「うちの土地、駐車場で貸してもいいよ」って言われたんですね。
それから、こうドミノ倒しに4,000坪もの土地を1枚の場所に借りれることができたんです。
それは我々のレンタカー屋では、めちゃめちゃ有利な話だった。
他の人達は、200坪の土地をあっち借りたりこっちに借りたりしてですね、そこに何台も車を置き分けて、それ例えばがお客さんが来ると、キャリアカーで運んだりして、お客さんが出発するところに持っていってですね、それの繰り返し繰り返しやっていかなきゃいけない。
そうするとですね、1日に1,000台の出発なんかできないですよね。
ところが僕らは一枚の場所にですね、めちゃめちゃたくさんの車が置いてあってですね、そんなことができてしまった。
でもこれはやっぱり外の人との付き合い方、ほんのちょっとしたお菓子ですよ。
多分何年か配ってましたけど、そんなたくさんのお金はかかってないと思います。
それからほんのちょっとしたまごころです。
「おばあちゃん暑いのに本当にお疲れ様、ご苦労様です、このお菓子東京から買ってきたから、よかったら息子さんと食べてね。」とかって言って。
まぁ、それがですね、人との付き合いにつながっていって、最終的には我々のトラベルレンタカーという会社のですね、沖縄で広大な土地を借りて成長戦略を描けた。
つまり多くのことは、人から始まるんですね。僕は結構いろんな商売をしてきました。
そんな中で社内や社外との人との付き合い、こういった人間関係がいかに企業の成長にとって大切か、これをずいぶん長いこと学ばせて頂きました。
皆さんもですね、是非気をつけてみてください。
ビジネスにおいて好き嫌いは不要
仕事をしていると、こう付き合わなければいけない人、たくさんあると思います。
でもですね、僕の友達がよく言うんですね。
銀行に対して、「なんでうちには金を貸さないんだ。」と。
「あいつは嫌な奴だ。」と。
でもそれ違うと思うんです。
それは自分の説明不足なんです。
僕らが銀行から借りる時には、本当に子細な資料を作ったり、過去の数字とか業界全体のことを比べて、自分たちがこういう事業で頑張って成功したいからお金を貸してほしいと。
それはね、もちろんお金を貸すっていうのと借りるって言うのは、上下関係みたいのがあるかもしれません。
それを、その一般的な中小企業の親父さん達はですね、「貸さないあいつは嫌な奴だ。」っていうんですね。
僕は違うんです。
借りれない自分が能力が足りない。
だから、もし僕らの事業でですね銀行が100%理解してくれれば、それは融資しようという気になります。
ところが、一般的な経営者はですね、そういった愚痴を述べながら、銀行に出した資料を聞くとですね、「去年の決算書出したよ。」とか投げ捨てるように言うんですね。
それでは銀行はなかなか事業に対して理解ができません。
「こんなのを担保に入れるから」って言ったよとかですね、確かにそれ担保価値はあります。
でも、銀行は担保を引き上げるというのは最悪の手段で、通常の返済をしてもらわないと困るんです。
それをですね、「担保があるのに何で貸さないんだ」とかですね、これまた本末転倒だと思うんですよね
そういったことですね主張している人をよく聞きますけども、まあ嫌な人とかいい人とかっていうのは、僕は全くビジネス上論外だと思います。
ビジネスで嫌な人とかいないんです。
例えば個人的な感情で、恋人として付き合う。
これは嫌な人だとか嫌いな人がいると思いますけれど、ビジネスの中には嫌な人だとか嫌いな人はいません。
お互いの仕事の仕方が違ったり、分析の仕方が違ったり、例えば立ち位置が違ったり、いろんなものが違うだけで、そこに好き嫌いは不要だと思っています。
つまり好きとか嫌いとかっていうのはなくてですね、もともとロジカルにこう考えて、その整合性が合うか合わないか、つまり、これが組み立てられるように、例えば相手がこれだとしたら、自分はこれを出して行かなきゃいけないってそこにこういうギャップがあるから、自分たちが好きとか嫌いとか思ったり、苦手な意識が出たりするんで、そこは非常にロジカルに考えていけば、苦手意識も減らせると思っています。
僕が経験した中から、皆さんの参考になればとお話しさせていただきました。
私自身の感想
ビジネスに人の好き嫌いは関係ないということ、それは、これまでの自分に対し、心から反省しなくてはいけない。
ビジネスでかかわっていく方々全員に対し、敬意をもって接するようになりたいと思いますね。
Youtubeでお話しされておられますので、直接お聞きになりたい方は、↓の画像をクリックしてください。