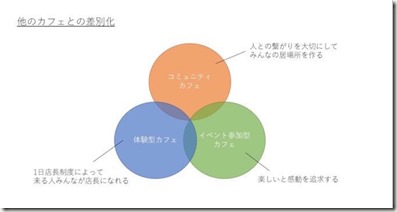飲食店を運営している人たちが、お客さまの立場に立つのは、簡単なようでとても難しい。
例えば、よく売上を上げる手段として、夕方以降営業していたお店が、お昼を営業するとします。
お昼にも来てもらいたいと、必死になって夜のお客さまに、「ランチ始めたんです、ぜひ来てください。」と言うでしょう。
それが果たして好奏するのでしょうか。
実際おこる現象は、「お昼そのお店に行って、夜もそのお店に行く」のでしょうか?
業種業態、立地によって多少の結果は違いがありますが、
例えば、居酒屋の場合、「昼行ったら夜はいかない。」という現象が起きます。
夜の顧客の希薄化、全体的な低客単価化、夜の売り上げ低下をもたらす場合が多いです。
人件費の総額は高騰します。
多少、新しい顧客を取ることができたとしても、全体的の利益低下をカバーできるには及びません。
運営をしている人は、なぜ見誤るのでしょうか。
それは、自店舗しか眼中にないからです。
自分の視点でしか見てないのです。
お客さまは、飽き性ですから、昼行った飲食店に夜行きません。
夜は、雰囲気や、会話を愉しみに食事に行くから、雰囲気を変えたいと思います。
「昼食べたからなぁ、、、、で夜の飲食の選択肢から外れます。」
素材や味付けはそれほど変わらない、雰囲気も変わらない場所に夜も昼も行かない。
そういう落とし穴を見逃してしまいます。
あと、メニューです。
例えば、お魚メインのお店で、お客さまの要望が、「肉料理が欲しい。」となった場合、
お客さまの要望に応えていくのでしょうか。
目の前の売上が欲しいばかりに、「お客様は神様」と言わんばかりに、
メニューの軸をずらしていけば、そもそも来ていただいていた顧客すら来なくなるような、
何がおいしいのかわからないお店になってしまうのです。
実際美味しいのかどうかは関係なく、なんでもやってしまうと、美味しいお店とは伝わらなくなるのですね。
でも、運営する側は、それが正しいと思い込んでしまいます。
ある一部の常連さまの要望には、はっきり言って「応えてはいけません。」
常連さまが経営を見てくれるわけではなく、そのお店にあったらいいなと思う、
自己都合の押しつけでしかないからです。
しっかり考えるべきは、コンセプトをメニューのどの範囲まできちんと担保するのか、、、、
という、考察がなくてはなりません。
中には、絞り込んだメニューでは戦えないという立地もあるでしょうが、
その場合は、コンセプトをキチンと見直したほうがよろしい。
そこにマッチするコンセプトを再構築し、店名、サブタイトルなどから、やり直すべきです。
コンセプトをどれほどシャープにするか、
コンセプトがわかりやすいか、メニューや内装が一致しているのか、
そういう面をしっかり組み上げて、お客さまにどう伝わっているのかしっかり顧客視点を持たなければならないのです。
どんなに品質のいいものを作っても、コンセプトがぼやける商品構成では、全く戦えません。
そうならないためにも、現場の視点ばかりではなく、オーナーや管理者がきちんと顧客視点を持って、
お店をTOPダウンで、導かなくてはいけません。
そういう場合は、現場のやる気を尊重しすぎて、ボトムアップしてはいけません。
逆に、ボトムの人がそういうことを理解している人ならば、ボトムアップすべきでしょう。
要するに顧客感覚がある人が、コンセプトを構築しなければならないのです。
もし、オーナーや責任者が、コンセプトミスマッチを起こしたくなければ、
たくさん食べ回ることです。
そして、顧客視点や、お店の肌感を大切にしなければいけません。