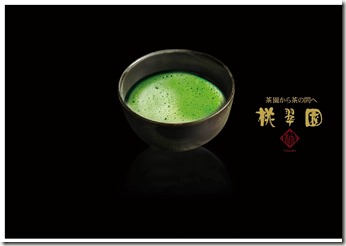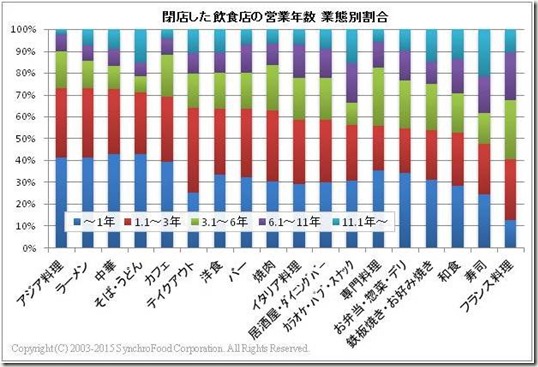今日は新店のご紹介です。
日本には、お茶の産地がたくさんあります。
10大産地と言われているのは下記です。
新潟県(村上茶)
埼玉県(狭山茶)
静岡県(静岡茶)
岐阜県(白川茶)
京都府(宇治茶)
奈良県(大和茶)
福岡県(八女茶)
宮崎県(日向茶)
鹿児島県(かごしま茶)
その産地それぞれ特徴があります。
しかし、それ以外にもお茶の産地はたくさんあって、
今日の主役は出雲茶の銘店「桃翠園」がカフェをオープンさせたという話です。
さて、出雲茶ってどういう特徴があるのでしょうか。
出雲茶とは
-
出雲茶の歴史
江戸時代も後半、歴代の松江藩主の中で松江藩中興の祖とされる大名茶人として名高い松平家7代藩主の松平治郷(1751~1818年)が、出雲にお茶を広げました。
「不昧公」の名で今も多くの人に親しまれていますが、これは1806年の隠居後に剃髪して名乗った号「不昧」からきています。
不昧公は、十代のころから茶の湯や禅学を熱心に学びました。
大名茶として知られる石州流を基本としながら、三斎流など他の流派にも接して自らの茶道観を確立しました。これが不昧流として今も伝わっています。
茶の湯の歴史における治郷の大きな功績は、それまで単に「名物」と呼ばれていた茶道具の名器をさらに細かく「宝物」「大名物」「中興名物」などと分類し、18巻にも及ぶ著書「古今名物類聚」にまとめたことです。
確かな審美眼による不昧公の活動は、近代の茶人たちにとって一つの目標とされ、日本茶道史上にその名を残しています。
-
出雲茶ゆかりの地
不昧公が松江城から船で渡ったとされる「観月庵」や、「明々庵」が200年の時を超えて、当時の茶道の一部を垣間見ることができます。
「明々庵」
※写真出展(200年分のおもてなし | 不昧公200年祭 特別サイト)ほか -
出雲茶の特徴
さっと蒸して苦みや香りを楽しみ、さっぱりとした風合いを味わえるのが出雲のお茶の特徴。
和菓子の消費量が松江市は金沢市に次いで全国2位。
和菓子を食べながらお茶を飲む文化がある地域なので、菓子とのバランスを考え、昔ながらの特性を生かしています。
-
桃翆園とは
島根県にて15haの茶畑を有し、緑茶の栽培から販売まで一貫して行っております。
-
出雲茶の美味しい淹れ方
一般に、熱い湯で茶を淹れると渋味の成分が早く抽出して渋味のある茶になります。
これは中級品以下の葉か番茶に適します。
低い温度でやや時間をかけて茶を淹れると、甘味、旨みが出てきます。
これは、テアニンといってグルタミン酸の一種ですが、玉露 や高級煎茶をだす時に適します。
| 茶量(g) | 湯量(ml) | 湯温(℃) | 時間(秒) | |
|---|---|---|---|---|
| 玉露(上) | 10 | 60 | 50 | 150 |
| 玉露(並) | 10 | 60 | 60 | 120 |
| 煎茶(上) | 6 | 170 | 70 | 120 |
| 煎茶(並) | 10 | 430 | 90 | 60 |
| 番茶 | 15 | 650 | 熱湯 | 30 |
| 焙じ茶 | 15 | 650 | 熱湯 | 30 |
※桃翆園さまサイトより
こんなに差が出るんですね、、、ちゃんとお茶を淹れて飲んでみなくてはと思います。
café國次郎(くにじろう)
今年はくしくも「不昧公」没後200年目の節目。
このcafé國次郎が記念すべきスタートにふさわしい年。
-
特徴
大きいセンターテーブルにはお茶の木が植樹されています。
そのお茶の木は、閉店後、お茶の木の体力温存のために、紫外線を当てます。
お茶の木の成長を眺めながら、お抹茶やスイーツをいただける、、、なんとも生産者直営らしい演出です。
-
メニュー
いずれも、自社茶園でとれた抹茶を使った商品。
・出雲抹茶ショコラテリーヌ
・出雲抹茶ジェラート
もちろん、お茶もご提供しております。 -
場所・営業時間
〒699-0624
島根県出雲市斐川町上直江1482
※出雲市斐川町上直江の「ゆめタウン斐川」近く。
TEL 0120-723-908
営業時間:10時~18時
定休日:毎週木曜日
自社農園を持つ強みは原価低減もさることながら、素材の活かし方を知っていること。
他の大都市圏で、展開されるとたくさんの方の支持が得られることと思いますが、
近くに行く機会があれば、メーカーならではの出雲抹茶ショコラテリーヌを絶対食べてみたいですね。